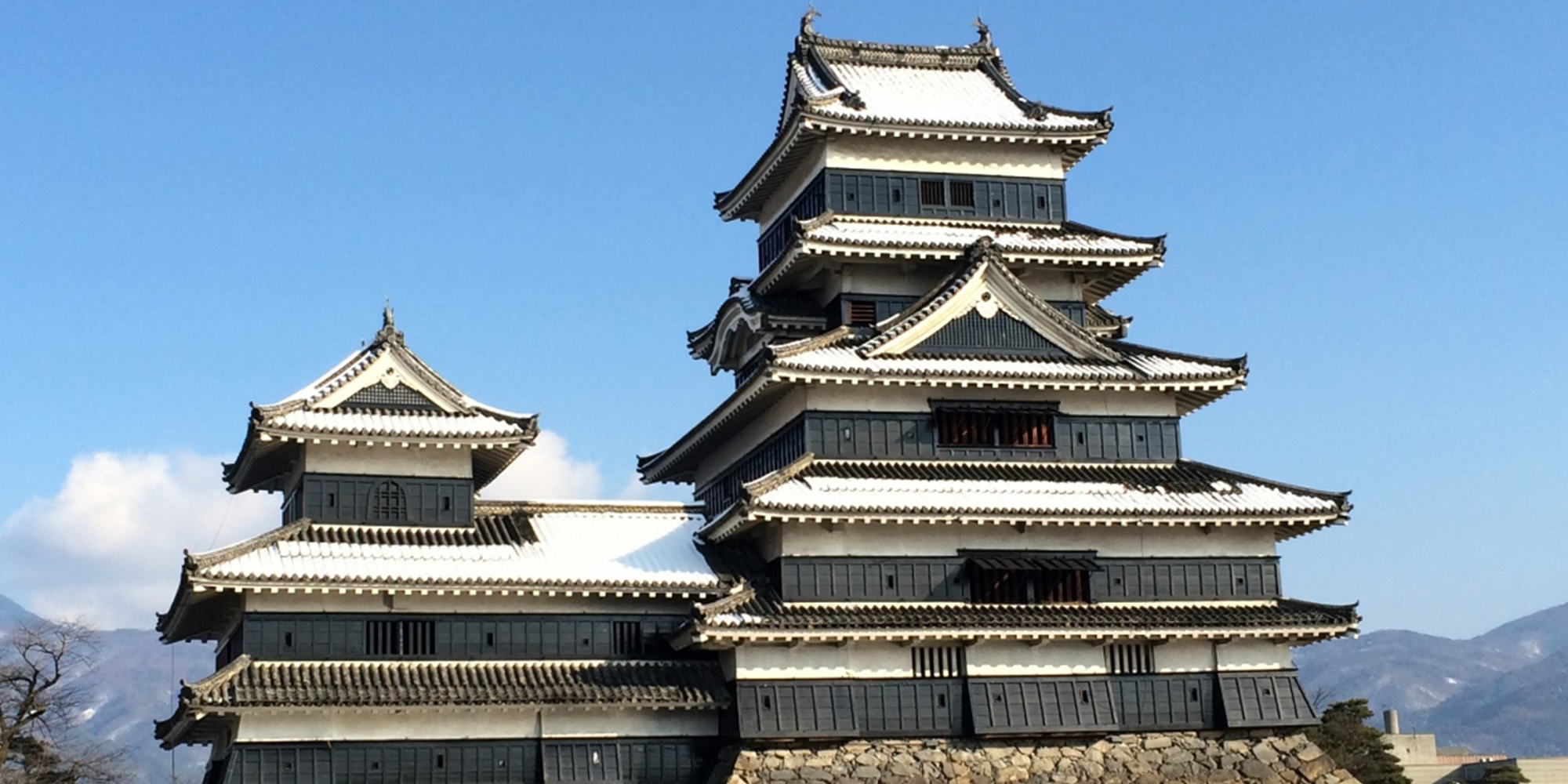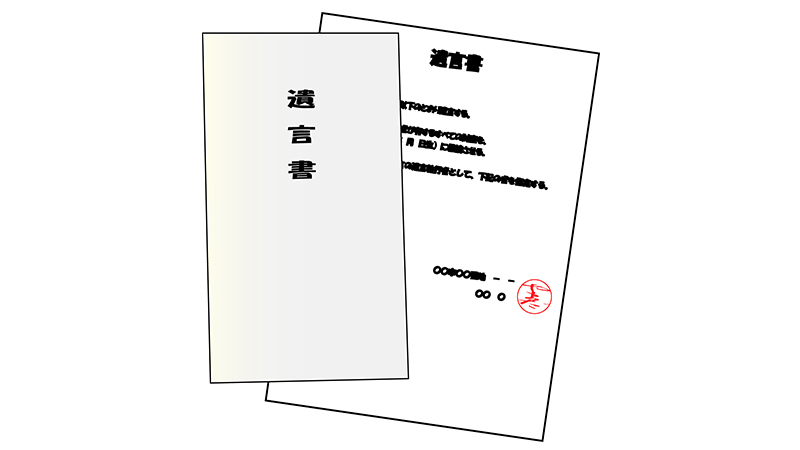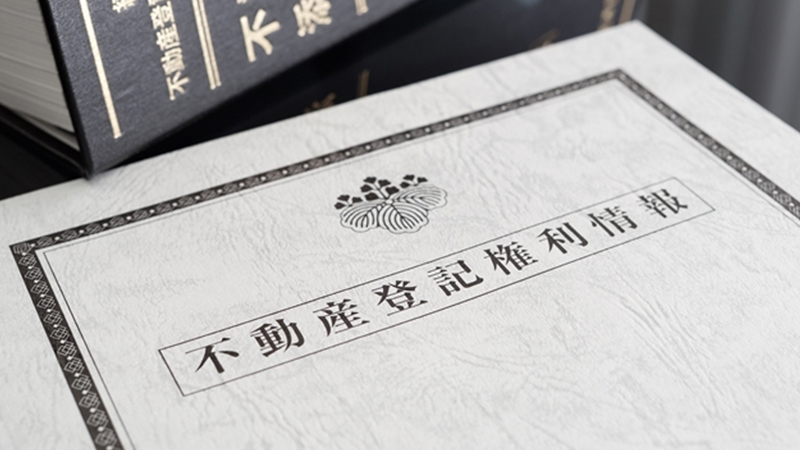ニュース
2月は「相続登記はお済みですか月間」です
最新トピックス
#39 不動産の個人間(直接)売買
トピックスは登記・相続・遺言・後見などに関するお役立ち情報が満載です。これまで取り上げたトピックスの全部がご覧いただけます。
相続登記義務化
相続登記が義務化されたことを受けて、当事務所では、広く皆様に相続登記をお手頃価格で行っていただけるよう取り組んでいます。
▼ 特集ページをぜひご覧ください ▼
取扱業務
SERVICE
こんなとき、当事務所はあなたのお役に立ちます。
日々の暮らしのなかで発生する様々な出来事・場面で、司法書士・行政書士があなたをサポートします。
詳細は、各項目をクリックしてご覧ください。
ご相談・ご依頼の流れ
FLOW
STEP1ご予約
STEP2ご相談
ご相談をお聴きいたします。1時間が目安です。
※初回相談は無料です。※資料はできるだけお持ちください。
STEP3お見積り
ご相談内容を検討して、料金のお見積りをお伝えします。
※この時点でお断りいただいても大丈夫です。STEP4受任・受託
お見積りの内容がよろしければ、受任・受託し、業務を開始いたします。
※お支払は、ご依頼内容に応じて前払いとさせていただくこともございます。アクセス
ACCESS